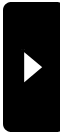面倒を見る
オレはよく “面倒を見る” という表現を使いますが (特に白蝋での染みさせる仕事で) これが、イマイチ
良く理解されて無いようなので チョットだけ・・・
 “白蝋” を使った仕事で 染料を染みさせる
“白蝋” を使った仕事で 染料を染みさせる
“調子” や “起こし” 等の仕事の場合
← この様に 白蝋の上の染料が
蝋にはじかれて 水滴となります。
(特に蝋を置いて最初に染料を引いた時)
写真で水滴の粒々が わかるでしょ。
 この粒々を そのまま放っておくと
この粒々を そのまま放っておくと
その粒々の感じが 蝋を落とした時に
残ってしまいます。 ・・・ので、
引き染 が終わってから 生地が “半乾き” に
なるまで、2~5分置きに 蝋の上の染料を
刷毛で 円を描くように 蝋に “摺り込む”
といった感じです。
 数回 繰り返してやると
数回 繰り返してやると
← こんな感じに 白蝋の上の染料の粒が
馴染みはじめます。
(最初の写真と比べるとかなり馴染んでるでしょ)
良くは分かりませんが、白蝋は柔らかいので
刷毛の毛で蝋の表面に “沢山の傷” が出来て
そこに染料が入り込むんじゃないかな???
 季節により 半乾き になるまでの時間は
季節により 半乾き になるまでの時間は
違いますが、大体 2~30分で 生地が
落ち着いて、蝋の上の染料の粒々が
← ほとんど気にならなくなります。
白蝋も 薄い部分は “傷んで来た” と
いった感じになります。
こんな事が オレの言う “面倒を見る” という事です。 分かって貰えたかなぁ~???
・・・追記?
化学染料の場合は 地色を一回で染めてしまうと想いますが、天然染料の場合 染(染料)、媒染と最低2回は
染めなくてはならないので、染める回数が増えてくると 更に蝋は傷んで来て 今度は 蝋の傷んだ部分の
“染料の被り過ぎ” に注意して下さい。 まぁ、イロイロ経験して下さい。 健闘を祈る!
技術 INDEX へ
良く理解されて無いようなので チョットだけ・・・
“調子” や “起こし” 等の仕事の場合
← この様に 白蝋の上の染料が
蝋にはじかれて 水滴となります。
(特に蝋を置いて最初に染料を引いた時)
写真で水滴の粒々が わかるでしょ。
その粒々の感じが 蝋を落とした時に
残ってしまいます。 ・・・ので、
引き染 が終わってから 生地が “半乾き” に
なるまで、2~5分置きに 蝋の上の染料を
刷毛で 円を描くように 蝋に “摺り込む”
といった感じです。
← こんな感じに 白蝋の上の染料の粒が
馴染みはじめます。
(最初の写真と比べるとかなり馴染んでるでしょ)
良くは分かりませんが、白蝋は柔らかいので
刷毛の毛で蝋の表面に “沢山の傷” が出来て
そこに染料が入り込むんじゃないかな???
違いますが、大体 2~30分で 生地が
落ち着いて、蝋の上の染料の粒々が
← ほとんど気にならなくなります。
白蝋も 薄い部分は “傷んで来た” と
いった感じになります。
こんな事が オレの言う “面倒を見る” という事です。 分かって貰えたかなぁ~???
・・・追記?
化学染料の場合は 地色を一回で染めてしまうと想いますが、天然染料の場合 染(染料)、媒染と最低2回は
染めなくてはならないので、染める回数が増えてくると 更に蝋は傷んで来て 今度は 蝋の傷んだ部分の
“染料の被り過ぎ” に注意して下さい。 まぁ、イロイロ経験して下さい。 健闘を祈る!
技術 INDEX へ
着物図案 ラフ前?
これはもうホントに 老婆心? 以外の何者でもないのですが・・・
ブログで知り合った 素人さん? が、ですけど、いきなり 雛形図案用紙 に “ラフ” というよりも前の
“あたり” とでもいうような感じのを描いていたもので・・・
 オレは図案の雛形を描く時は (本チャン)
オレは図案の雛形を描く時は (本チャン)
← クロッキー紙に 実寸と同縮尺の 型紙?
を写して 雛形を描いてます。
コピーして それに描けば 型紙 を写す手間が
省けるのですが、色を付けた時の感じがイマイチ
ピンと来ないので 毎回 型紙を写してます。
(本チャンへと入る準備運動でもあるのですが)
 しかし、上の “本番雛形” へ入るまでには
しかし、上の “本番雛形” へ入るまでには
広告の裏とか、コピー用紙の裏とかに
← フリーハンドで簡単な 雛形を描いて
それに大雑把な ”あたり” を入れます。
(5秒位で簡単に描けます)
コピーが安くなったとはいえ あたり は
これで 充分間に合います。
 もともとは捨ててしまう紙・・・
もともとは捨ててしまう紙・・・
惜しくも無く、気の済むまで描きまくれます。
それで、感じがつかめたら徐々に “かたち”
を詰めて行って、いよいよ本チャンに入ります。
今回はホントに 老婆心ですが “エッ???”
と想ったもので・・・
技術 INDEX へ
ブログで知り合った 素人さん? が、ですけど、いきなり 雛形図案用紙 に “ラフ” というよりも前の
“あたり” とでもいうような感じのを描いていたもので・・・
← クロッキー紙に 実寸と同縮尺の 型紙?
を写して 雛形を描いてます。
コピーして それに描けば 型紙 を写す手間が
省けるのですが、色を付けた時の感じがイマイチ
ピンと来ないので 毎回 型紙を写してます。
(本チャンへと入る準備運動でもあるのですが)
広告の裏とか、コピー用紙の裏とかに
← フリーハンドで簡単な 雛形を描いて
それに大雑把な ”あたり” を入れます。
(5秒位で簡単に描けます)
コピーが安くなったとはいえ あたり は
これで 充分間に合います。
惜しくも無く、気の済むまで描きまくれます。
それで、感じがつかめたら徐々に “かたち”
を詰めて行って、いよいよ本チャンに入ります。
今回はホントに 老婆心ですが “エッ???”
と想ったもので・・・
技術 INDEX へ
小張の裏技?
人に教えて上げると 多くの方が “ヘェ~・・・” と感心されるので、チョット御披露。
“友禅伸子” とは別に 生地を弛まない様に張る伸子を オレ達 (ウチの系列だけ???) は
“小張(こばり)” と呼びますが、それにもイロイロな種類がありまして・・・

↑ 上から 帯・着物等を染める 普通の小張2種、 暖簾などの広幅 を染める小張、
風呂敷の様な大きなサイズの広幅 を染める小張2種
(ちなみに 短 40cm、 広幅 56cm、 長 105cm)
もっと多くの種類の 小張が販売されてますが、全部を揃えるのは 金銭的にも場所的にも大変。
そこで “貧乏染師” は考え出しました! (まぁ誰でも考え付くと思いますが・・・)

← 欲しいサイズの小張に 近いサイズの
小張2本を用意して・・・

← セロテープを巻き付けます。
最低でも 3ヶ所 は巻き付ける部分が欲しいです。
(3回位は巻き付けといた方が、シッカリします)
 ← こんな感じで使用します。
← こんな感じで使用します。
この方法を教えて上げると 皆一様に感心してくれるので、教え甲斐があります。
少ない材料でも 工夫次第で多くの使い方ができます。 (←自慢したりして・・・)
更に良い事には、“張り加減のテンション” の調整が出来るのです。
“厚い生地” で 少しきつめに張りたい時には 長めに組み合わせ、
“薄い生地” で あまり強く張りたくない時には 短めにすると 張り具合を調節できます。
なかなか便利な方法なので、知らない方が居たら 教えてあげて下さい。 チャンチャン!
技術 INDEX へ
“友禅伸子” とは別に 生地を弛まない様に張る伸子を オレ達 (ウチの系列だけ???) は
“小張(こばり)” と呼びますが、それにもイロイロな種類がありまして・・・
↑ 上から 帯・着物等を染める 普通の小張2種、 暖簾などの広幅 を染める小張、
風呂敷の様な大きなサイズの広幅 を染める小張2種
(ちなみに 短 40cm、 広幅 56cm、 長 105cm)
もっと多くの種類の 小張が販売されてますが、全部を揃えるのは 金銭的にも場所的にも大変。
そこで “貧乏染師” は考え出しました! (まぁ誰でも考え付くと思いますが・・・)
← 欲しいサイズの小張に 近いサイズの
小張2本を用意して・・・
← セロテープを巻き付けます。
最低でも 3ヶ所 は巻き付ける部分が欲しいです。
(3回位は巻き付けといた方が、シッカリします)
この方法を教えて上げると 皆一様に感心してくれるので、教え甲斐があります。
少ない材料でも 工夫次第で多くの使い方ができます。 (←自慢したりして・・・)
更に良い事には、“張り加減のテンション” の調整が出来るのです。
“厚い生地” で 少しきつめに張りたい時には 長めに組み合わせ、
“薄い生地” で あまり強く張りたくない時には 短めにすると 張り具合を調節できます。
なかなか便利な方法なので、知らない方が居たら 教えてあげて下さい。 チャンチャン!
技術 INDEX へ